主治医となる医師による依頼翌日の訪問が基本
ゆう在宅クリニックの概要を教えてください。
ここ保土ケ谷区今井町の本院の他、旭区二俣川の旭院、神奈川区三ツ沢南町の横浜院、瀬谷区阿久和西の瀬谷院と4院があります。4院全体で、医師は私を含めた常勤医が20人、非常勤医も同数程度、看護師は8人、事務系職員が約25人でスタッフ数は70人を超えます。患者数は月間約1400人で9割が高齢患者さん、1割が脊髄損傷や神経難病などの若年患者さんです。年間でのお看取り数は約700件で、2025年1月は月間で75件でした。
当院の特長は「断らないこと」「すぐに行くこと」です。電話応対ではなく、足を運び、担当者の顔を見せることを基本としています。依頼から初診までのスピードが速く、ほとんどの場合、翌日には対応しています。ケアマネさんから依頼が入ると、主治医となる医師が翌日には患者さんの元を訪れ、患者さんとご家族の希望を聞きながら、診療方針・費用の見積りを出し、合意が取れればそのまま在宅診療契約を結びます。ほとんどの場合は、そのまま在宅診療に入ることになりますが、まれに合意が取れないこともあり、そういった場合は往診1回のみのカウントになります。
一般的な在宅診療では、事務員が先に契約内容を説明しに行き、費用や診療方針の合意を取れた後に医師が診療を開始することが多いのですが、当院はそれではスタートが遅くなると考えています。患者さん、ご家族が困っているならすぐに駆けつけたい。診療が遅れることで、病状が悪化してしまう場合もあり、ご依頼があれば医師がすぐに駆けつけることを基本としています。

開業当初から分院を増やすという目標でやってこられたのですか。
分院を増やしたいという目標があったわけではなく、気付いたらここまで増えていたという感覚です。「断らない」が私の診療姿勢であり、依頼があれば医師自らすぐに訪問するという当院のやり方が地域に知れ渡っていくごとに、あちこちから依頼が増えていった感覚です。2007年の本院開業以来、患者数は順調に伸びていき、今現在も増え続けている状況です。
患者さんからの多様なニーズに応えるため、当院には異なる専門分野を持つ医師たちが在籍しています。そこもケアマネさんたちから「ゆうさんに任せておけば大丈夫」と好評を得ている点だと思います。正直、内容によっては当院では対応できない場合もあるのですが、「とにかく在宅診療ならゆうさんに相談」と地域から最初に声をかけられる存在になっています。
現在の専門医の内訳は、私を含む泌尿器科専門医が5人、外科4人、麻酔科3人、内科4人、救急救命医2人、整形外科1人、精神科1人、神経内科1人で、合計21人の常勤医です。高齢患者さんには泌尿器系トラブルが頻発しますので、主訴対応の他にも泌尿器科医としての知識や技術が役立つことが多いです。
特に寝たきり患者さんにはバルーン管理が必要になりますから、泌尿器科の専門知識が直接生かせます。また、泌尿器科は臓器別専門科でありながら全身状態との関連が強いため、患者さん全体を診る在宅医療の視点と共通点があり、泌尿器専門医と在宅診療医には高い親和性があると感じています。後輩の泌尿器科医たちが私を頼ってきたり、彼らの知り合いの別科の専門医が応募してきたりで、気付けばここまで大所帯になっていました。
5人の専門医仲間が集まり各々在宅クリニックを開業したが…
開業された背景を教えてください。
病院に勤務していた頃、終末期医療のあり方に疑問を感じていました。多くの患者さんが「家に帰りたい」と望んでいるのに、病院で最期を迎えざるを得ない状況が少なくありませんでした。そして、そこで提供される医療は「点滴をして寝かせているだけ」という状態が多く、患者さんのためというより、病院の都合に合わせた医療のようでした。
「死んでいないという状態を維持するための医療」ではなく、自然な形で寿命を迎えるための医療、生活の延長線上にある医療も必要ではないかと、私は思っていました。しかし、自然な死を受け入れるため、あえて何もしない医療を選択することは病院勤務医としては難しく、開業を考えるようになりました。
当時は国が在宅医療を推進し始め、在宅療養支援診療所の制度が創設された頃でした。在宅医としての開業を考える医師仲間も多く、グループを組んで在宅開業する話が仲間の一人から持ち上がりました。在宅医療には往診が不可欠ですが、ソロプラクティスの開業医には24時間対応の往診対応は難しいので、そこをカバーするためにグループを作ろうと。シフトを組んで往診に当たるのは良策と思い、外科医、内科医、泌尿器科医など5人の専門医仲間が集まり、それぞれで在宅クリニックを開業することを決めました。
私の「ゆう在宅クリニック」は、2007年に立ち上げました。「ゆう」には、You(あなた)、友(友達)、優(優しい)、悠(悠々)など、いろいろな言葉があてはまります。患者さんたちが、それぞれに感じるままの文字をあてはめてもらいたいと思い、ひらがなで「ゆう在宅クリニック」と名付けました。
開業医グループでのシフト往診体制は続いているのですか。
残念ながら方向性の違いから、グループでのシフト往診はすぐに終わってしまいました。往診の受け止め方に大きな違いがあったのです。私はとにかく「すぐ行く」ということを重視し、電話対応ではなく、患者さんに顔を見せることが重要だと考えていました。だから他の医師が自分の患者さんを往診する時も、自分と同じ対応をしてくれるものだと思っていました。しかし、そうではなかったのです。グループを組んでの開業から3年も経たないうちに、5人 いた仲間は2人だけになってしまいました。
やはり何に重点を置くかでクリニックの方向性は変わります。私は患者さんの生活に深く関わり、家族や地域から信頼されることに一番重きを置いています。
開業して、日が経つほどに患者数も増えていき、医師一人の限界も感じていました。自分が医療活動を通して何をしたいのか、医師として大切にしていることもはっきりしてきました。方向性が同じでないと上手くいかないということも分かりましたから、志を同じくする仲間を募っていこうと決めました。
「患者さんに寄り添い、すぐに行動する」という私の理念に賛同できる医師が集まってくるようになり、2019年旭院、2023年横浜院、2024年瀬谷院と開院させていきました。

オンコールは常勤医10人以上のチームで分担
ゆう在宅クリニックでの勤務の特長を教えてください。
開業医と勤務医の間という新しい働き方ができることです。ソロプラクティスの在宅医療では24時間対応の負担が大きく、病院勤務では自分のペースで診療できないというデメリットがあります。当院ではそういったデメリットをなくし、開業医と勤務医のメリットのみが感じられる勤務体制を採用しています。
当院の給与体系は完全出来高制ですから、やればやっただけの収入が得られます。加えて診療担当医としての裁量権が大きいので、自身の診療スタイルをダイレクトに患者さんに提供できます。自身の時間管理はもちろん、患者さんの管理についても、それぞれの医師に任せていますから、開業医と変わらないほどの自由でやりがいのある働き方 が実現できます。一方、適度に働きつつ仕事と家庭を両立したいという医師にも、柔軟に対応できる環境を整えています。
オンコール(緊急対応)は、常勤医師10人以上のチームで分担するため、プライベートな時間も確保できます。チームにはさまざまな専門分野の医師が揃っているので、分からないことがあれば相談できますし、当院は日本在宅医療連合学会、日本緩和医療学会の研修施設になっていますから、勤務しながらの専門医取得も可能です。組織としての安定性と個人の裁量・自由度の両方を享受できるので、「患者さんに寄り添い、すぐに行動する」という当院の基本姿勢に共感できる医師にとっては、働きやすく、やりがいのある職場環境であると思っています。
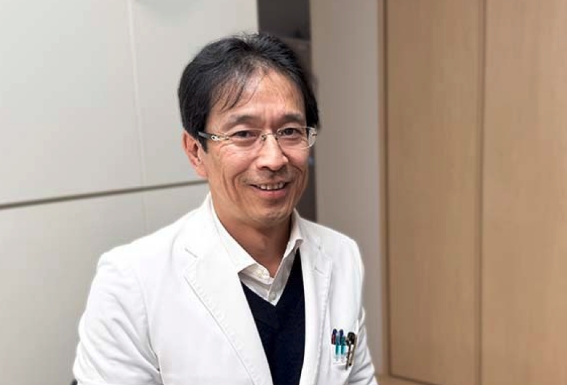
クラウド型電子カルテ「モバカル」開発に携わられた背景を教えてください。
複数の医師でオンコール体制を組むようになると、情報共有の問題が浮上してきました。初期の頃は患者情報を記載したデータをUSBメモリに入れて、週末のオンコール担当医師に手渡すなどしていましたが、セキュリティの問題もあり、非常に苦労していました。
そうした状況の中、2011年にNTTプレシジョンメディシン株式会社からクラウドカルテを一緒に開発したいという申し出があり、迷わず協力させてもらうことにしました。当院が直面している問題と要望を細かく伝え、それに沿って作り上げていただいたのが「モバカル」です。開発者の方が非常に優秀で、私たちの要望をスピーディーにシステム化してくれたおかげで、すぐに実践で使えるカルテが2012年に完成しました。
このシステムの導入により、どこにいても最新の患者情報にアクセスできるようになり、複数医師によるチーム在宅医療が本当の意味で可能になりました。在宅医療の質と効率を大きく向上させた転機となったと言っても、過言ではありません。
医療スキル以上に人材管理が大変、目下組織改善中
課題はありますか。
組織の拡大に伴う管理体制の構築が、現在の最大の課題です。現在当院は常勤医21人、非常勤医も約20人、事務スタッフや看護師を含めると70人を超える組織となっています。2024年に初めて「辞めたい」という常勤医師が出てきました。3カ月前に退職の相談はあったものの、2007年の開業以来、退職を希望する常勤医はいなかったので、正直ビックリしました。そして、後任医をどうするかという問題に初めて直面しました。
人が増えるほどに、スムーズなコミュニケーションが難しくなってきています。以前なら私の一声で、すぐに全体の統制がとれましたが、今では「聞いていません」ということが起きるようになりました。特にオンコール対応時には、主治医以外の医師が患者を診ることになり、医師が増えるほどに対応の統一性を保つことが難しくなっています。
医療スキル以上に人材管理が大変です。早急に今の体制を見直し、各部門の責任者を決めて、管理体制を整えていく必要があると感じています。現在コンサルタントを入れて、組織改善に取り組んでいます。
今後の展望について教えてください。
患者さんのニーズに応えながら、自然な成長を遂げていきたいと思っています。「断らない」「すぐに行く」というこれまでのやり方通り、地域から必要とされる医療を提供し続けていくつもりです。
私は現場が好きなので、私自身の目標としては、なるべく早く以前のような診療に打ち込めるスケジュールを取り戻していきたい。そのためにも、早急に組織改善を進め、それぞれの部門に責任者を配置することで、私自身の勤務環境を整えていく必要があります。
また、非常勤でいいので、皮膚科と眼科の専門医にチームに加わってもらいたいと考えています。寝たきりの患者さんでは皮膚疾患を患っている方がほとんどで、高齢による眼科疾患も多いですから、週に1~2回でも非常勤の専門 医に入ってもらえれば、より総合的な医療が提供できるはずです。
介護士不足が懸念される中、多職種での連携を大切にし、チームとなってお互いを尊重しながらそれぞれの役割で患者さんを支えることが重要だと感じています。医療だけ一人よがりに突っ走ることなく、介護、福祉職と常に相談しながら、患者さん一人一人のQOLを高める医療を提供し続けることが当院の使命だと考えています。地域のニーズに応えるかたちで、横浜市の在宅医療を担う中核施設へと、自然な形で成長を続けていきたいと思っています。
(※記事内容は令和7年1月現在のものです)

